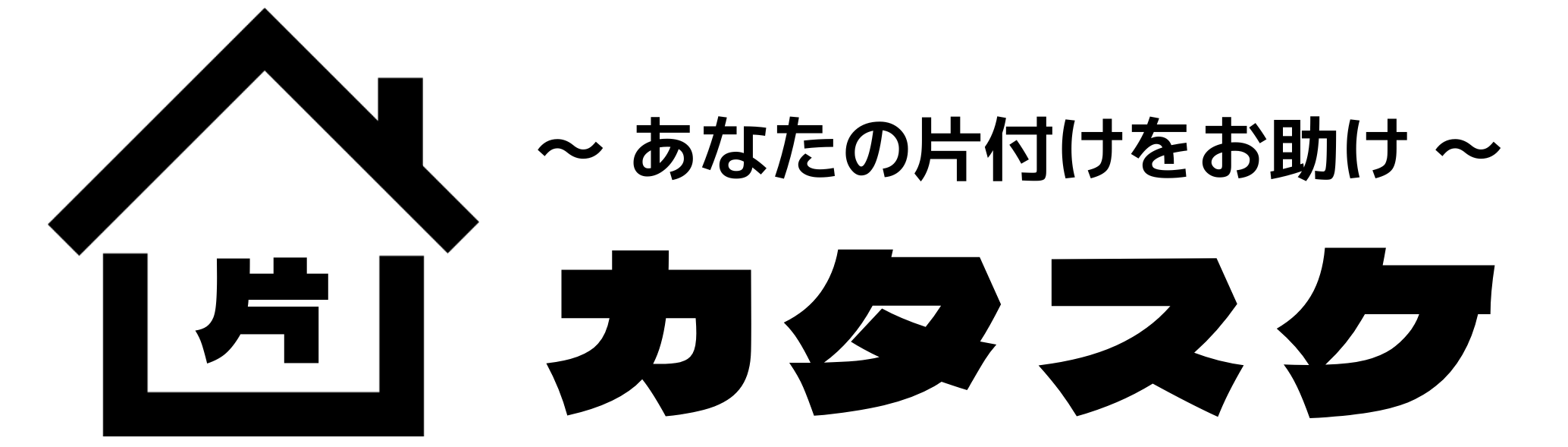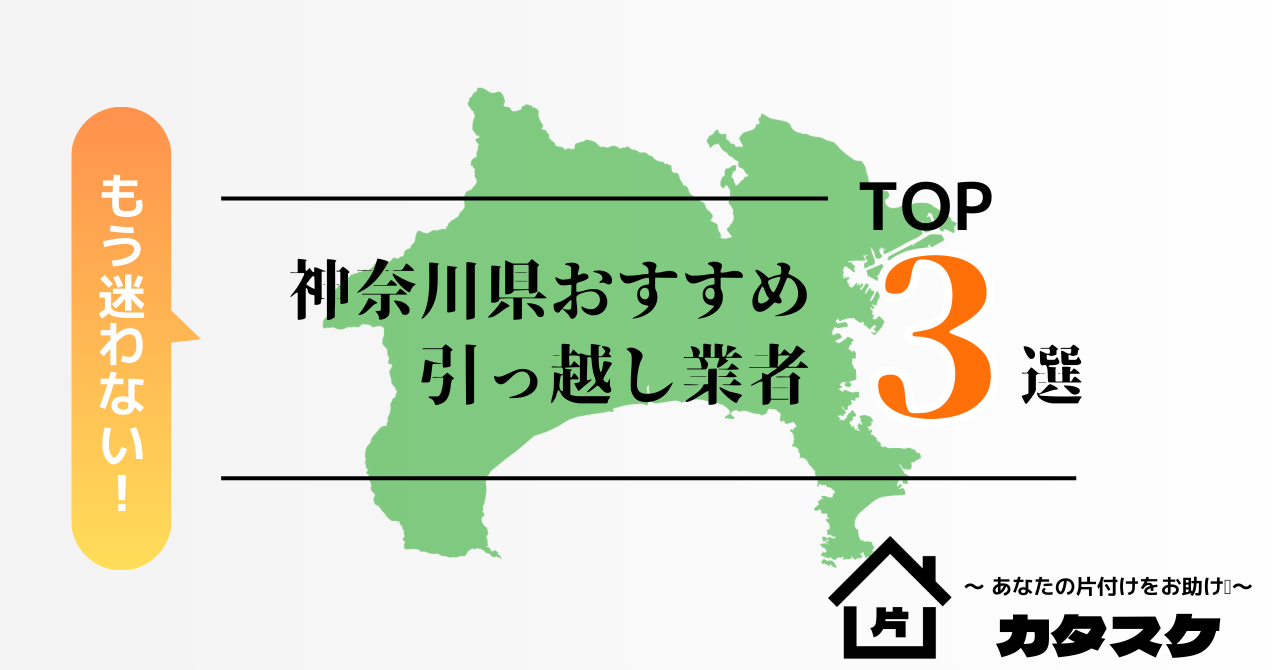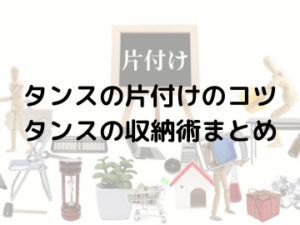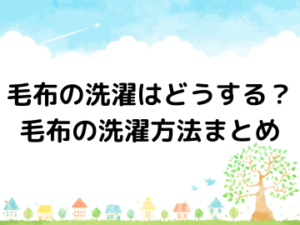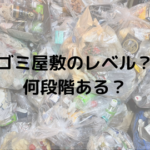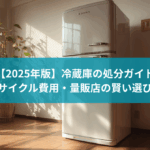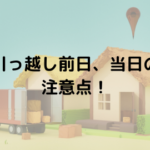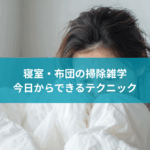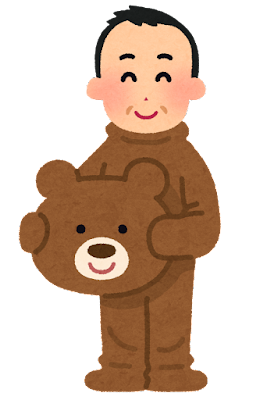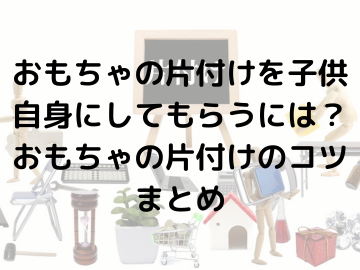
目次
はじめに
子供が自分の部屋やおもちゃを片付けられない…そんな悩みを持つご家庭は多いのではないでしょうか。
「片付けなさい!」と何度言ってもなかなか行動してくれず、気がつけば親が代わりにやってしまう。すると子供は「片付けはお母さん(お父さん)がやるもの」と認識してしまい、自主的に動けなくなります。
しかし、片付けの習慣は小さいうちに身につけておくことが大切です。自分の持ち物を自分で管理できるようになると、責任感や自立心も育ち、将来の生活力にもつながります。
この記事では、子供が「自分で片付けられるようになる」ための具体的な工夫やコツをたっぷり解説していきます。今日から実践できるアイデアも盛り込みましたので、ぜひご家庭で試してみてください。

子供に片付けを任せるメリット
- 自立心が育つ
自分の持ち物を管理する力は「自分のことは自分でする」という自立心を養います。 - 物を大切にする気持ちが芽生える
物の置き場所を意識することで、無くしたり壊したりすることが減ります。 - 学習習慣につながる
机の上が整理されていると勉強にも集中しやすく、生活全般のリズムも整います。
子供に片付けをしてもらうためのコツ

1. 片付けやすい環境をつくる
子供が片付けられないのは「めんどくさいから」だけでなく、「やり方が分からない」場合もあります。
- おもちゃ箱はフタのないタイプにする
- 棚の高さは子供が手を伸ばして届く範囲に
- 仕分けはシンプルに「おもちゃ」「本」「工作」「ぬいぐるみ」など大きなくくりで
複雑な分類にすると、子供はすぐに挫折してしまいます。
2. ラベルや写真を活用する
字が読めない子には写真ラベルがおすすめです。
例:ブロックのおもちゃ箱にはブロックの写真を貼る、絵本棚には絵本のイラストをつける。
「どこに戻すか」が一目でわかるようになるので、迷わず片付けができます。
3. 遊びの延長として片付ける
「片付け=つまらない作業」と思わせない工夫が必要です。
- タイマーを使って「1分間でどれだけ戻せるかゲーム」
- 親子で一緒に「どっちが早く片付けられるか競争」
- お気に入りの音楽をかけながら片付けタイム
楽しさをプラスすることで自然と習慣づけができます。
4. 小さな成功体験を積ませる
最初から「全部片付けなさい!」はハードルが高すぎます。
「今日はブロックだけ」「本棚だけ」など部分的に区切って達成感を味わわせるのが効果的です。
できたときにはしっかり褒めてあげることで、次もやる気につながります。
5. 親が“見本”を見せる
子供は親の行動をよく見ています。親がいつも整理整頓していると「片付けは当たり前」という意識が自然に育ちます。
逆に、親が片付けを後回しにしていると、子供も「片付けなくてもいい」と思ってしまいます。
6. ご褒美制度をうまく活用する
片付けが習慣になるまでは「ご褒美」も効果的です。
- シールを貼っていくチャート方式
- 片付けたら絵本を一冊読んであげる
- 一週間続いたら好きなおやつを選べる
ただし「ご褒美がないとやらない子」にならないよう、少しずつ自発的な行動につなげるのが大事です。
年齢別の片付けの工夫
- 3〜5歳
→ 分類は大まかに。写真ラベルや「大きい箱ひとつ」で十分。 - 小学校低学年
→ 学用品や文具も自分で管理させる。タイマー片付けゲームが効果的。 - 小学校高学年
→ 学習机や衣類の整理なども任せてみる。自主性を尊重しつつ「一緒に見直す日」を作る。
子供が片付けやすくなる収納グッズ・教育グッズの紹介

子供に「片付けなさい」と言っても、収納場所がわかりにくかったり、出し入れが面倒だと長続きしません。そこで役立つのが 子供専用の収納グッズや教育アイテム です。実際に取り入れてみると「片付け=楽しい!」に変わり、自主的にやってくれるようになります。
1. カラフルでわかりやすい収納ボックス
- 透明や半透明のボックスに、おもちゃの写真やイラストのラベルを貼ると、どこに片付けるかが一目でわかります。
- 軽いプラスチック製なら、子供でも持ち運びがラク。
2. 絵本ラック・ブックスタンド
- 本棚が高い位置にあると子供は取りにくく、出しっぱなしになりがちです。
- 表紙が見えるタイプの絵本ラックなら「しまいたい」「選びたい」という気持ちを刺激できます。
3. トイカート・おもちゃワゴン
- おもちゃをまとめて運べるワゴンがあると、遊ぶ場所に移動して、遊んだ後はそのまま戻すだけで片付け完了。
- キャスター付きなら小さい子でも簡単に動かせます。
4. 片付け教育に役立つ絵本や教材
- 「お片付けの習慣」をテーマにした絵本を読み聞かせると、遊びながら自然に学べます。
- 片付けをゲーム化した教材やボードもあり、親子で一緒に楽しめるのが魅力です。
5. ごほうびシール・チェック表
- 片付けができたらシールを貼る仕組みにすると、子供が達成感を持ちやすいです。
- 習慣化をサポートしてくれるアイテムとして活用できます。
このようなアイテムを取り入れると、子供は「やらされる片付け」から「自分でできる片付け」へとステップアップしていきます。
まとめ
子供に「片付けをしなさい!」と口で言うだけでは、なかなか行動につながりません。
大切なのは「片付けやすい環境を作ること」「やり方をわかりやすく教えること」、そして「片付けは楽しい・気持ちいい」と感じさせてあげることです。
小さな成功体験を積ませながら、褒めて認めてあげることで、子供は「片付けは自分でできる!」という自信を持つようになります。親が先回りして全部やってしまうのではなく、あくまでサポート役に徹することが、子供の自立につながります。
今日からできる小さな工夫で、子供が自分で片付ける習慣を育てていきましょう。それは単なる部屋の整理だけでなく、将来にわたる“生活力”を身につける大切な第一歩になります。