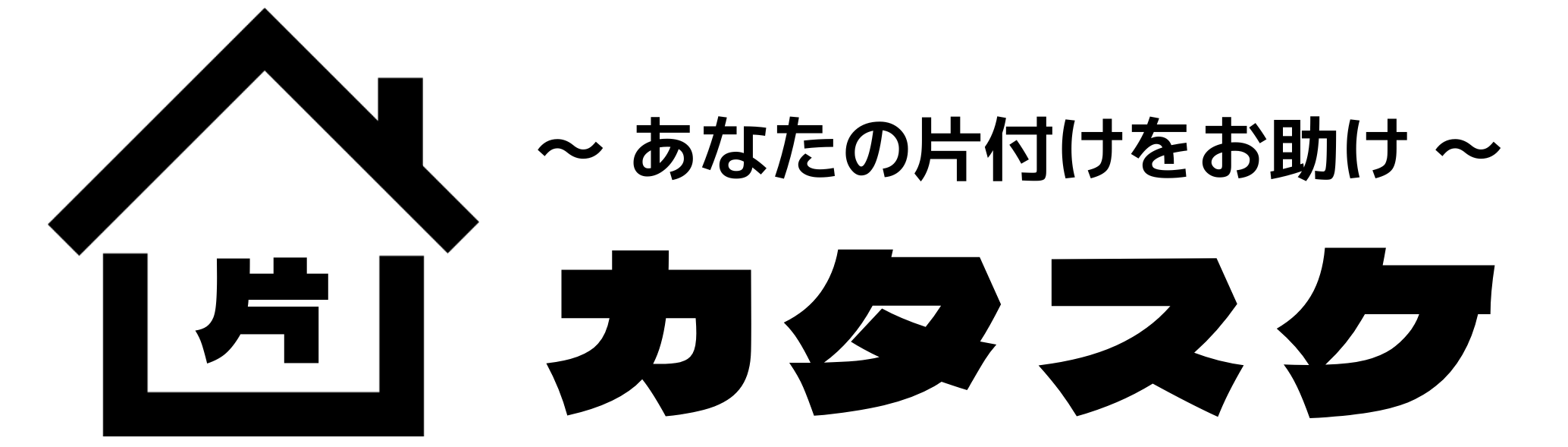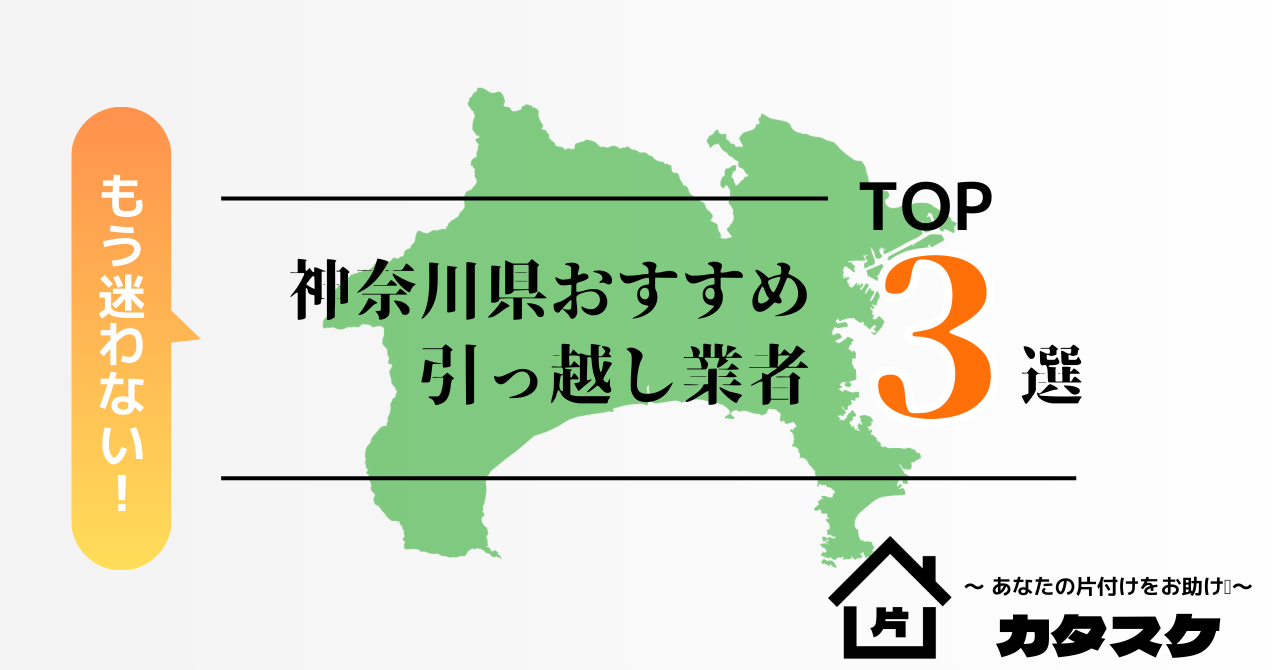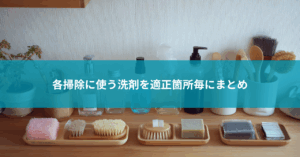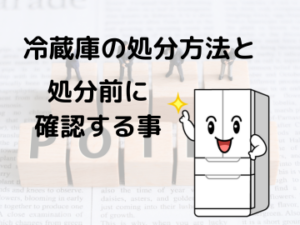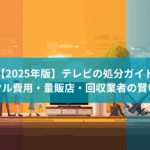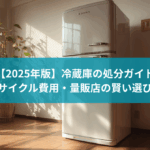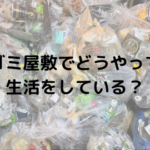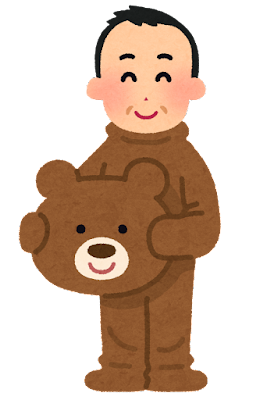はじめに
台車とは、荷物や器具、機材などを移動させるための移動式の機器のことです。様々な用途に合わせた種類があり、選ぶ際にはその用途や条件に応じた適切なものを選ぶ必要があります。本記事では、台車の用途や選び方について詳しく解説します。
台車の用途

台車には様々な用途があります。例えば、以下のようなものがあります。
物流業界における搬送作業
荷物の仕分けや運搬、積み込み・降ろしなどの作業において、荷物を効率的に移動させるために利用されます。
建設現場における材料運搬
建築現場や土木現場などでは、建材や資材などを移動させるために台車を使用することがあります。
飲食店における食器運搬
飲食店では、食器や調理器具、食材の運搬などに使用されます。特に、大量の食器を運ぶ場合には、効率的に運ぶために欠かせないものとなっています。
病院における医療器具運搬
病院では、医療器具や薬剤、病院用品などを移動させるために、台車を使用することがあります。医療器具の大きさや形状に合わせたものが必要となります。
台車の種類と特徴を徹底比較【折りたたみ・キャリーカート・業務用】

プラットフォーム型台車(重量物に強い定番タイプ)

特徴
底面がフラットで広く、大型荷物や重量物の運搬に適した台車。工場や物流倉庫など、業務現場で最も一般的に使われています。
- 倉庫・工場での重量物搬送
- 引っ越しや大型家具の運搬
- 建設現場での資材移動
- 広い積載面で安定感がある
- 耐荷重が大きく、200~300kg以上の荷物にも対応
- フラットな形状で荷物の積み降ろしがしやすい
- サイズが大きく、収納性が低い
- 狭い通路や段差では取り回しにくい
👉「とにかく重いものを安全に運びたい」「業務用として長時間使いたい」人に最適です。
キャリーカート型台車(軽量・操作性重視)

特徴
比較的コンパクトで軽量、キャスターの動きがスムーズな台車。個人利用や軽作業に向いています。
- オフィスや病院での荷物運搬
- 飲食店での配送・仕入れ作業
- 日常の買い物やアウトドア
- 軽量で女性や高齢者でも扱いやすい
- 折りたたみ式や伸縮式のモデルも豊富
- 車に積んで持ち運びやすい
- 耐荷重は50~100kg程度と小さめ
- プラットフォーム型に比べると安定性が劣る
👉「軽い荷物を日常的に運びたい」「省スペースで扱いやすい台車が欲しい」人におすすめです。
折りたたみ型台車(家庭・収納スペースが限られる人に最適)

特徴
使わないときにコンパクトに折りたためるのが最大の特徴。収納場所が限られる家庭やオフィスに人気があります。
- マンション・家庭での荷物運搬
- オフィスやイベント会場での一時的な使用
- 車に積んで出先で使用
- 折りたたんで立て掛け収納できる
- 軽量で持ち運びやすい
- 日常利用から引っ越しまで幅広く対応可能
- 耐荷重は150kg前後が多く、大型荷物には不向き
- 構造上、安定性は固定式に劣る
👉「使う頻度は少ないけど、いざという時に便利な台車が欲しい」人にぴったりです。
特殊用途台車(タンク・シリンダー・クレーン型など)

特徴
特定の用途に特化して設計された台車。液体、ガスボンベ、重量物の吊り上げなど、専門性の高い現場で使われます。
- タンク型:液体や薬品の安全な移動
- シリンダー型:ガスボンベ・消火器の運搬
- クレーン型:重量物の吊り上げ・移動
- 専用設計で特定の荷物を安全に運搬可能
- 作業効率が大幅に向上
- 危険物や特殊資材を扱う現場で必須
- 汎用性がなく、一般家庭ではほぼ不要
- 専用用途のため価格が高い場合が多い
👉「工場や医療現場など、特殊な荷物を扱う環境」に欠かせないタイプです。
失敗しない台車の選び方5つのポイント
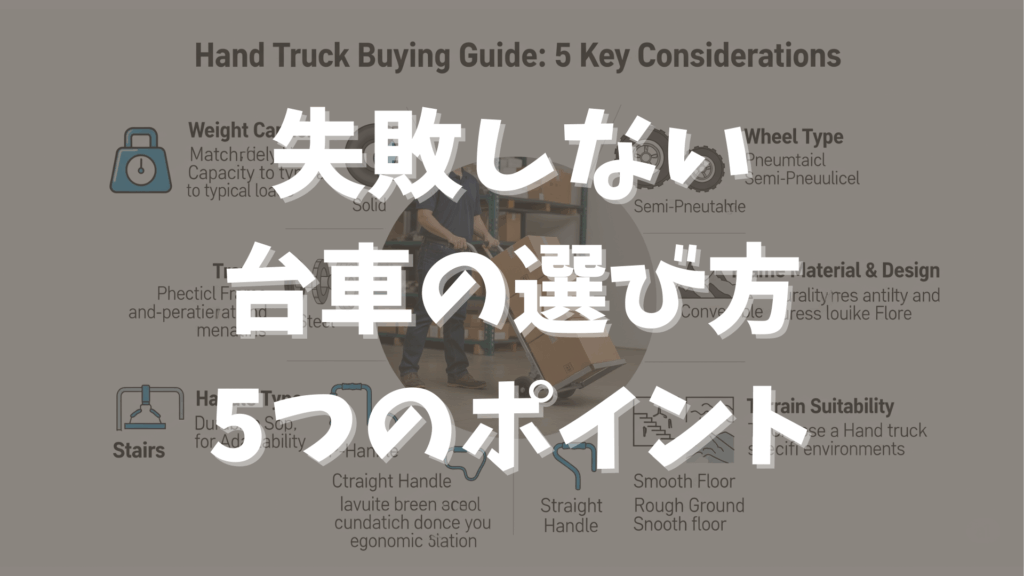
1. 耐荷重の確認(安全性を左右する最重要ポイント)
台車選びで最も重要なのが「耐荷重」です。荷物の重量に対して余裕のあるモデルを選ばないと、キャスターの破損や転倒につながり危険です。
- 日常使用(家庭・オフィス):耐荷重100kg以下
- 業務使用(倉庫・配送):150~200kg程度
- 重作業用(工場・建設現場):300kg以上
👉「少し余裕を持った耐荷重」を選ぶことが、台車を長持ちさせる秘訣です。
2. 台車サイズの選定(荷物の大きさ+使用環境に合わせる)
荷物のサイズと使用する場所に応じて台車の大きさを選びましょう。大きすぎると保管や取り回しに困り、小さすぎると荷物が安定しません。
- 小型(60×40cm前後):家庭やオフィス用に最適
- 中型(70×50cm前後):一般業務用、引っ越しや荷物搬送に便利
- 大型(90×60cm以上):重量物・大量の荷物をまとめて運搬可能
👉「使う環境の広さ(エレベーターや通路の幅)」も必ず考慮してください。
3. 移動環境への適合性(屋内・屋外・段差対応)
台車は使う環境によって最適な仕様が異なります。特にキャスター(車輪)の種類は移動の快適さを大きく左右します。
- 屋内中心:静音キャスター付き(病院・オフィス向け)
- 屋外利用:大径キャスター(悪路・アスファルトでも安定)
- 段差が多い環境:エアタイヤや大型キャスターで衝撃吸収
👉「どこで使うか」を具体的にイメージして選ぶのが失敗しないコツです。
4. 静音性能のチェック(住宅・オフィス利用なら必須)
キャスターの素材によって、走行音は大きく変わります。マンションや深夜の作業でうるさい台車を使うと、近隣トラブルの原因になりかねません。
- TPR樹脂キャスター:最も静音性に優れ、滑らかな走行
- エラストマー樹脂:床にタイヤ痕が付きにくい
- グレーゴムキャスター:静音性と耐久性のバランス型
👉「集合住宅・オフィス」で使うなら、静音キャスター搭載モデルを選びましょう。
5. 収納性と利便性(折りたたみ・ブレーキ機能の有無)
使用頻度や保管スペースに合わせて、収納性や追加機能をチェックするのも大切です。
- 折りたたみ式:収納場所が限られる家庭・オフィスに最適
- ブレーキ機能:傾斜やトラック荷台での安全確保に必須
- 立て置き収納機能:玄関や倉庫の隅に省スペース保管可能
👉「折りたたみ式+静音キャスター+ブレーキ機能」が、家庭でも業務でも最も使いやすい組み合わせです。
台車に関するよくある質問(FAQ)
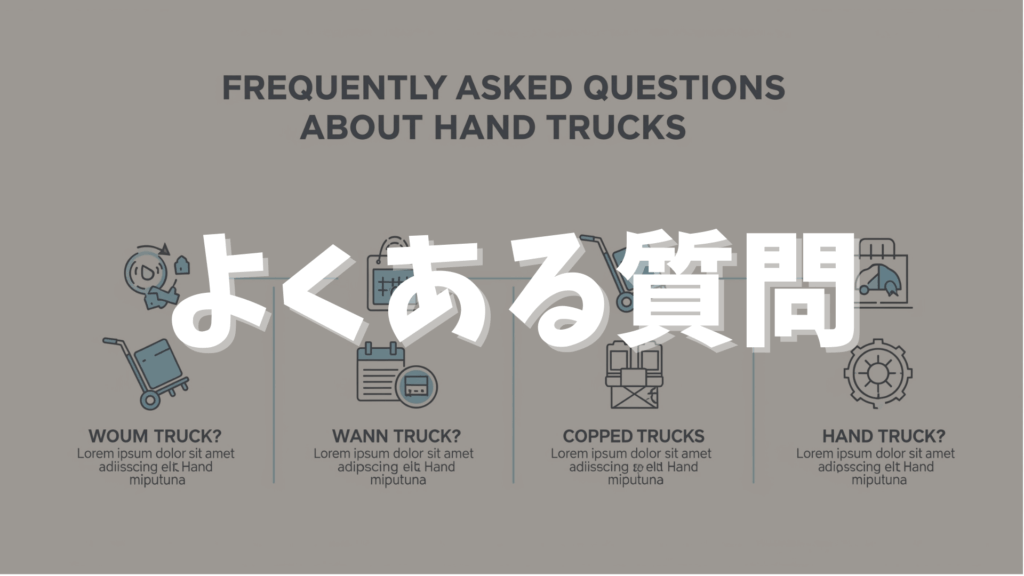
Q1. 台車の耐用年数はどのくらい?
A1. 一般的には5〜10年が目安です。
ただし使用頻度や環境によって大きく変わります。毎日重い荷物を載せる業務用では数年でキャスター交換が必要になることもあります。
ポイント
- キャスターの摩耗やゴム割れが主な寿命要因
- 本体フレームは丈夫なため、部品交換でさらに長く使える
👉 定期的にキャスターやボルトを点検すれば、耐用年数を大きく延ばせます。
Q2. キャスターの交換はできる?
A2. ほとんどの台車でキャスター交換は可能です。
特に業務用モデルは交換を前提に設計されています。
- 交換時はメーカー純正品を使うのが安心
- ネジ径や取付サイズを確認することが大切
- 純正品が高い場合は互換品でも代用可能
👉 消耗品であるキャスターを交換すれば、台車本体を長く使えます。
Q3. 屋外使用は可能?
A3. 屋外でも使用可能ですが、キャスター選びが重要です。
雨や砂利道など、屋外特有の環境に合わせて選ばないと故障や摩耗が早まります。
屋外使用のポイント
- 大径キャスター:段差や砂利道でも安定
- エアタイヤ:衝撃吸収性が高く不整地でも走行可能
- 使用後は泥や水分を拭き取り、サビ対策をすると長持ち
👉 倉庫の屋外搬送やイベント現場など、屋外利用が多い方は「屋外専用台車」を選ぶのがおすすめです。
Q4. 折りたたみ式と固定式どちらがおすすめ?
A4. 使用環境と頻度によっておすすめが変わります。
- 折りたたみ式台車
- メリット:収納しやすい、省スペース
- デメリット:耐荷重や安定性はやや劣る
- 向いている人:家庭・オフィス・マンション住まい
- 固定式台車
- メリット:頑丈で安定性が高い、耐荷重も大きい
- デメリット:収納に場所をとる
- 向いている人:倉庫・工場・引っ越し業者など業務利用
👉 「収納性重視なら折りたたみ」「安定性・耐久性重視なら固定式」と考えると失敗しません。
Q5. 静音キャスターはどの程度静か?
A5. 標準キャスターに比べて走行音を大幅に軽減できます。
特にTPR樹脂やエラストマー製キャスターは、コンクリートやフローリングの上でも「ゴロゴロ音」がほとんど気にならないレベルです。
- マンションの廊下や深夜の作業でも騒音トラブルを防げる
- 病院やオフィスでの静かな環境に最適
- 床への傷やタイヤ痕も付きにくい
👉 「家庭用・オフィス用」「夜間利用」が多い人は、静音キャスター搭載モデルを選ぶと快適です。
まとめ
台車は、様々な用途に合わせた種類があり、その用途や条件に応じた適切なものを選ぶことが重要です。荷物の重量や大きさ、移動場所、収納場所、耐久性や安全性などを考慮し、適切な台車を選ぶことで、効率的な荷物運搬が可能となります。
また、台車の使用に際しては、適切な使い方やメンテナンス方法にも注意が必要です。使用前に荷物の積載量や台車の耐久性を確認し、安全に使用することが重要です。また、定期的に清掃や点検を行い、安全に使用できる状態を保つことも大切です。